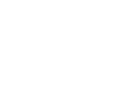認定特定非営利活動法人がんサポートコミュニティー
認定特定非営利活動法人がんサポートコミュニティー
がんと共に生きる
Living with Cancer
支援者の声
あなたはひとりではありません。わたしたちも応援しています。
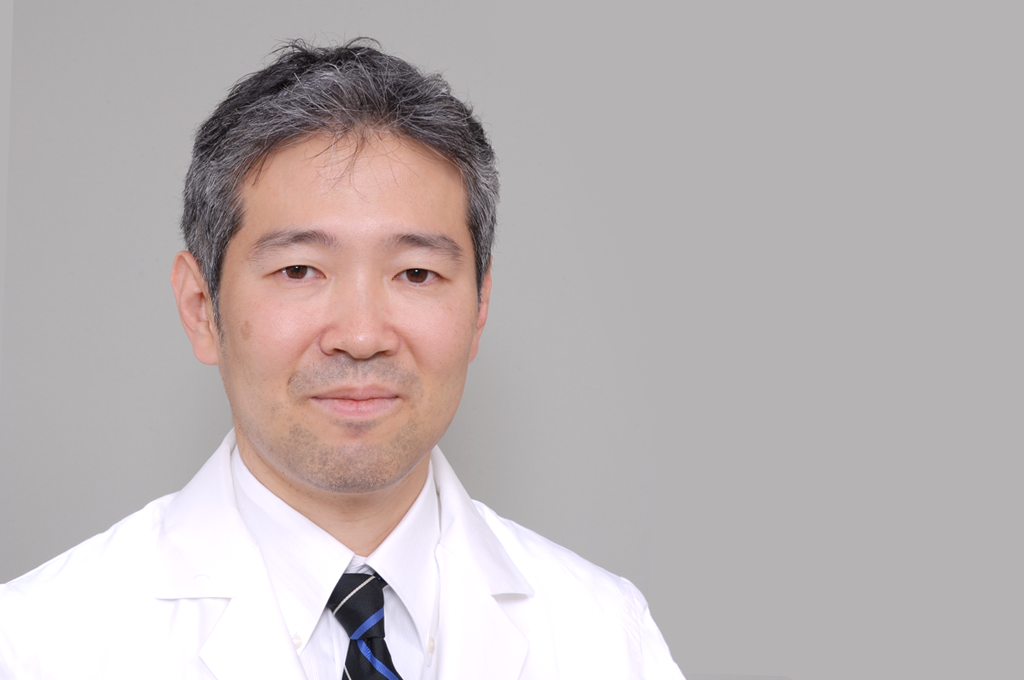
がん体験後にこころがたどる道筋~精神腫瘍医の視点から~
清水 研
がん研究会有明病院腫瘍精神科部長
(投稿当時、国立がん研究センター中央病院
精神腫瘍科長)
私は精神腫瘍医としてがんに罹患された方とそのご家族の診療を担当しています。今まで3500人以上の方のお話を伺ってきた経験から、がん体験後に多くの方のこころがたどる道筋は次のようなものであると思っております。もちろん、正解というものはなく、100人の方がいらっしゃれば100通りの道筋がありますので、自分には当てはまらないと思われる方は読み飛ばしていただければと思いますが、何かのご参考になりますと幸いです。
突然のがん告知を受けると、それまでは当たり前であったこと、つまり「健康で平和な毎日が続く」という世界が突然変貌し、目の前には様変わりした世界、さまざまな喪失や、死の予感を伴う現実が姿を現します。世界が様変わりしたことに対して、心理的な観点から2つの課題に取り組むことになります。
1つ目の課題は、「健康で平和な毎日が失われた」という喪失と向き合うことです。最初はその事実を認めたくないという気持ちが働くでしょうし、圧倒的な現実の前に茫然自失になるのも無理がないことです。悔しさがあふれ、果てしない悲しみが湧いてくることもあるでしょう。喪失と向き合うという課題に取り組む際には、負の感情がとっても重要な役割を果たしますので、感情に蓋をしないことが大切です。
「こんなことはたいしたことではない」と自分に言い聞かせ、表面的には平静を装う人もいます。しかし、つらい気持ちを押し込めても、それがなくなるわけではなく、心の奥底でくすぶり続けてしまいます。ですので、「我慢しているのもしんどくありませんか。自分の心のメッセージを信じ、泣き叫びたがっている心を自由にしても大丈夫ですよ」と、徐々にお伝えするようにしています。私の世代の男性は「泣くことは弱い人間がすることだ」という刷り込みを受けてきたように思います。なので、自分が感情を表すことに抵抗があったり、周囲の人が泣くと戸惑ったりするのですが、泣くことは喪失と向き合うための大切なプロセスなのだと思います。
2つ目の課題とは、「様変わりした現実をどう過ごしたら、そこに意味を見いだせるのか」を考えることです。嵐のような悲しみや怒りが完全になくなることはないでしょうが、「残念ながらこの事実は変えられないんだ」という諦めや絶望に近い感覚が生まれたとき、2つ目の課題への取り組みが始まります。毎日を過ごせることがあたりまえのことではないという感覚は、一日一日を大切に生きようという姿勢につながることもあり、その一日をどのよう生きたらよいのか、真剣に考えるようになる方もいらっしゃいます。1つ目の課題と2つ目の課題は同時に進行しますが、徐々に悲しみや怒りが弱まっていき、新しい人生を考えるという方向にシフトしていかれます。
精神腫瘍医として私が第一に心がけるのが、その人がどのような悩みを抱えておられるのか、十分に理解しようとすることです。そのためには、時間をかけていろいろなことを聞かなければなりません。その人がどんな人生を歩んできて何を大切にしてきたか、がん体験がその人の人生にどのような影響を与えたか、そして今何に最も困っているのか。私なりにその方の悩みが理解できたと思ったときにはじめて、「○○さんの中では、がんになることでこういう問題が起きたと感じられ、とても困っておられるのですね?」という考えを伝えます。私の言葉に対して、相手が心の底から「そうなんです!」と言ってくだされば、最初の大切なステップがうまくいったことになります。なぜなら人は、「自分の悩みを誰かが理解してくれた」と思えたときに、苦しみが少し癒えるからです。
しかし、どれだけ経験を積んでも、寄り添うことは簡単ではないと感じております。ですので、「寄り添わなければならない」のではなく、「寄り添おう」という姿勢を持ち続けることが大切なのではないかと思っております。
ここまでお読みいただき、感謝申し上げます。以上まとめまして、私が一番みなさまにお伝えしたいことは次のようなことです。①がん告知などのつらい出来事に向き合うときに大切なことは感情に蓋をせず、きちんと悲しむことである。②負の感情が徐々に和らいでいく中、新たな人生について考えるというプロセスが始まる。③苦しんでいる人に寄り添うことは簡単なことではないが、「寄り添おう」とする姿勢が力になる。
がんサポ通信・第38号(2020春)掲載

がんのゲノム医療、どこまでわかる? どう向き合う?
渡邊 清高
帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科 病院教授 (寄稿当時、帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科准教授)
がんのもととなるがん細胞は、もともと私たちの体をつくるための設計図といえる遺伝子の傷から起こることがわかっています。近年の研究の進歩により、がんがさまざまな遺伝子の異常から発生していることがわかってきました。一方で、遺伝子の異常を検査によってとらえることで、治療効果や副作用の予測、再発のリスクなどとの関連がわかってきました。「がんのゲノム医療」では、がんに関わる遺伝子情報全体(ゲノム)をもとに、診断や治療、予防に活用することで、より効果的で効率的な医療を行うことを目指しています。
2018年から全国に質の高いがんゲノム医療を実施する施設として、がんゲノム医療中核拠点病院やがんゲノム医療連携病院が全国に設置されました。
2019年6月に保険承認された「遺伝子パネル検査」では、がんの組織を用いて、100を超える多数の遺伝子を同時に調べ、遺伝子変異の有無からそれぞれの患者さんにとって効果が期待される治療薬の候補が示されます。具体的にはEGFRやRAS、BRAFなどがん細胞の増殖に関わる遺伝子や、BRCA、p53などのがん抑制遺伝子、ALKなどの融合遺伝子の有無や発現の変化を評価します。これらの遺伝子は、これまで肺がんや大腸がん、乳がんなどで治療効果を予測する遺伝子として検査が行われたものです。例えば非小細胞肺がんの治療において、EGFR遺伝子変異の有無を調べることによって、選択する薬剤(ゲフィニチブ、エルロチニブなど)の適応について判断がなされます。治療効果の期待される患者さんをあらかじめ予測することが可能になります。逆に治療効果が期待できない薬剤の使用を防ぐことにつながり、副作用のリスクを減らすことができます。
発がんやがんの増殖に関わる遺伝子は、どの場所にがんが発生するか(肺がん、消化器がん、乳がん、骨や筋肉のがんなど)に関わらず、共通の変化が見られることがあることから、同じ薬剤の効果が期待できる場合があり、個々の患者さんのがんの特徴に合わせた薬剤の選択が可能になります。
2019年6月に公的保険の適応となったがん遺伝子パネル検査は、標準治療がない(希少がんなど)、または標準治療を終了している(見込みを含む)患者さんが対象になっています。これまで効果が期待できる治療薬がなかったがんに対して、新たな候補薬剤が見つかる可能性が期待されています。全国の拠点病院では、質の高いがんゲノム医療を実施する体制や、相談や遺伝カウンセリングを受けられる体制の整備が急ピッチで進められています。
このように、これまでは治療が難しい状態であった患者さんに新たな治療薬が見出される可能性が示される一方で、新たな課題もあります。遺伝子パネル検査はあくまでも「検査」であり「治療」ではありません。必ずしも治療に結びつく遺伝子変化が見つかるわけではないこと、何らかの遺伝子異常が見つかっても、それに対応した適切な薬剤が存在しない場合や海外でしかアクセスできない、国内で未承認あるいは保険適用外であったりする場合があります。遺伝子変異に対応した薬剤が、臨床試験段階である場合には、臨床試験や治験に参加するなどの方法も考えられますが、時期や対象などの条件があり、必ずしも効果的な治療につながるとは限らないといえます。また、検査を受けた患者さんのフォローアップをどのように行っていくかなど、課題も多く残されています。
遺伝子パネル検査では、遺伝性のがん、家族性の腫瘍に関係する遺伝子変異が発見される可能性があります。治療薬につながる可能性がある一方で、こうした情報をどのように患者さんやご家族・血縁者の方に伝えるか(あるいは伝えないか)、病気の発症やリスクと関わる情報を適切に取り扱うかという課題も指摘されています。治療が一段落したあとのフォローアップ、治療の継続について、遺伝的な素因があることがわかった場合には、リスクを適切に評価した上で、フォローアップ、適切な予防や検診プログラムの提示などにつなげることができると考えられています。私たちは、がんのゲノム医療に基づいて得られる新しい情報を、医療者や専門家の支援を受けながら、適切に活用していくことが求められています。
がんサポ通信・第37号(2019夏)掲載

患者の安心を繋ぐ二人主治医制の勧め
廣橋 猛
永寿総合病院 がん診療支援・緩和ケアセンター長
「緩和ケアは末期になってから受けるもので、まだ私には早い。」そう考える患者からの声が多く聞かれる。しかし、それは間違っている。緩和ケアが対象とするのは、痛みといった身体のつらさだけではない。抗がん剤の副作用や、これからどうなっていくだろうという漠然とした不安や、仕事やお金のことなど現実的な問題。すべてのがん患者にとって切実な問題に取り組み、生活の質を高めることを目標としている。長く治療に取り組むがん患者にとって、緩和ケアは早期から伴走すべきパートナーである。
また、このような声も多く聞かれる。「がん治療は終了だから緩和ケアに行けと言われ、見捨てられた気分になった。」これは少なからず現実に起こり得る会話。悲しいかな、がん治療医の中で、このような説明をする医師がいるかもしれない。この見捨てられ感を無くすために、私が提唱しているのが「がん治療医と緩和ケア医の二人主治医制」である。
二人主治医制とは、がん治療医と緩和ケア医が並行して診療を行うことを意味する。抗がん剤治療のために通院している患者は、たとえばがん治療医の診察を隔週で受けながら、緩和ケア医の診察を2ヶ月おきに受ける。緩和ケア医との診察では、さまざまなつらさの緩和に関わる話題から、いつか病状が悪化したときにどう過ごすか、いわゆる終活の話題まで多岐にわたる。がん治療についての意見を求められることもある。そして、もしいつの日か抗がん剤治療の継続が難しくなったとき、いわゆる緩和ケアが主体となる時期を迎えられたとき、がん治療医から緩和ケア医へ主な関わりをバトンタッチしていくことになる。どちらかだけでなく、並行して診療を行いながらゆっくりとバトンタッチしていくので、患者にとっても見捨てられるという感覚を和らげることができるかもしれないし、安心して診療を受けることができるだろう。
病状が悪化したときに備えるのは、縁起でもないという考えもあるだろう。しかし、特に再発・転移しているほとんどのがんは、一生病気と付き合っていく必要がある。いつか積極的な治療を続けられなくなるかもしれない。であるならば、もしものとき自分が困らないような備えをしておくことは、むしろ安心につながるのではないだろうか。緩和ケア医は、患者にとっての最善を期待しながら、最悪に備える支援を約束したい。
このような早期から緩和ケアを受けることの重要性を示した報告もある。世界で一番有名な医学雑誌に掲載された研究では、ステージⅣの非小細胞肺がんの患者に、治療しながら緩和ケアを受けていた群と、そうではない群を比較したところ、緩和ケアを受けていた群の方が約3ヶ月生存期間の延長が認められた。なぜ緩和ケアを受けた方が長生きできたかというと、効果が乏しい抗がん剤治療を無理に続けず、適切な時期に終了することで、余計な体力を消費せずに済んだからと言われている。将来の準備ができていれば、そして患者個々の価値観を尊重して相談できる相手がいれば、少しでも自身にとって望ましい過ごし方を選択できるのだ。
ぜひ緩和ケアは死を連想するからと忌み嫌うのではなく、皆さんが良く生きるために活かしていただきたい。皆さんが関わる病院や、地域の中で味方となる緩和ケア医を探してみてほしい。
がんサポ通信・第36号(2019春)掲載

約20年のかかわり
中川 信幸
がんサポートコミュニティー副理事長 (株式会社PIJIN常勤監査等委員)
この度の理事会で副理事長を拝命することになりました中川です。微力ながらがんサポートコミュニティー(以下、「がんサポ」と略称します。)のお役に立てるよう努めますのでよろしくお願いいたします。
まず私が参画することになった経緯からお話させていただきます。
私がまだホギメディカルの役員をしていた2000年頃だと思いますが、がんサポ(当時は「ジャパン・ウェルネス」との名称でした。)の創設者である故竹中文良先生にお会いする機会があり、医療関係の仕事柄非常に興味を持ちました。ホギメディカルは、ご存知の方も多いと思いますが、病院の手術用の消耗品等を扱う会社で、日本全国のほとんどの病院に商品を納入しています。赤坂2丁目にホギメディカルの自社ビルがあり、当時のがんサポの事務所が赤坂3丁目にあり、すぐ近くにありました。
故竹中先生は私財を投げうって献身的にがんサポを支えておられ、創成期のご苦労をヒシヒシと感じました。セミナー等の会場探しにもご苦労されており、「会議室が使えないか?」とか「寄付ができないか?」とか私も色々考えて、当時ホギメディカルの社長に相談したこともありしました。ただ、会社は全方位外交で特定の団体等を支援するのは避けたいとの意向があり、残念ながらご協力はできませんでした。そこで、私は個人的に事あるごとにお手伝いさせていただくようになったのです。
2018年6月16日、松﨑圭祐先生(要町病院腹水治療センター長)を招いて、がんサポと同じく米国に本部を持つ膵臓がん患者さんを支援するNPO法人パンキャンジャパンと共催しました第8回がんを学ぶセミナー「あきらめないがん治療―腹水治療」では、念願かなってホギメディカルの立派な会議室を使わせていただきました。
現在、私が支援しているPIJIN(ピジン)という会社は、「QRコードを活用した多言語情報サービス」を提供しています。海外からの方々も多く参加されています大阪マラソンの時にそのサービスを提供いただき、がんサポの取り組みを英語・簡体字・繫体字の三か国語で発信することができました。大阪マラソンの他のオフィシャル寄付先団体等では全く考えもしないアイデアだったのでは?と自画自賛しています。
がんサポは、活動規模はそれほど大きくなっていませんが、たくさんの皆様のご支援をいただき、財政基盤は強固になり、がん患者さんやそのご家族の方々に心理社会的なサポートを続けることができています。大変ありがたいことだと感謝しています。
私自身が管理系の人間ですので、どうしても財務面からがんサポを見てしまいます。わが国では、まだ寄付文化が根付いているとは言い難い現状だと思います。有意の多くの団体が財政難で苦労し、活動が充分にできないのが現状です。その中で、がんサポが現在のように継続してがん患者支援を提供できるほどに財務基盤が強固になった大きな要因は、私は大井事務局長を抜きに語れないと思っています。欧米のNPOや財団等には専門の財務担当者がいて、寄付活動や集まった資金の運用等を実施して、資金的に活動を支えていると聞きます。何といっても資金がなければ、どんなに素晴らしい活動であっても滞ってしまいます。また大阪マラソンは第1回大会から8年連続してオフィシャル寄付先団体としての指定を受け、多額のご寄付をいただいています。
このようにいただいた多くのご支援を広く他の活動にも広げていく必要があるとも思っています。例えば、たとえがんになっても働き続けることができるように、就労の問題提起や環境づくりにも目を向けなくてはなりません。さらに、私の友人が訪問看護・在宅医療の祐クリニックという医療法人を立ち上げていますが、自宅に居ながらの闘病・術後ケアも重要な課題だと思います。他の団体等との連携も強力に推し進めていかなくてはなりません。
私は残念ながら医学についての知識は全くありません。ただ、管理系、財務系の知識はそれなりにありますので、がんサポの組織の運営に関してお役に立ちたいと思っています。
皆さま今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
がんサポ通信・第35号(2018夏)掲載
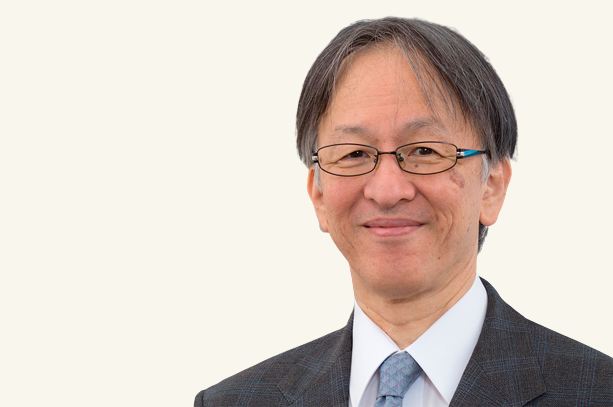
多方向から患者さんを支えるがん診療とは?
片山 和宏
市立貝塚病院総長
(寄稿当時、大阪国際がんセンター副院長兼
臨床研究センター長)
私の叔父である竹中文良が、ジャパン・ウェルネスを立ち上げて、早17年が経ちます。先日、ジャパン・ウェルネスから発展されたがんサポートコミュニティーの大井さんからご連絡をいただき、認定NPO法人になられたことや大阪にも活動を拡げられているのを知り、感慨深いもの感じております。
私自身は、現在大阪国際がんセンター(旧大阪府立成人病センター)で、副院長・臨床研究センター長として、臨床研究のサポートを行うとともに、肝胆膵内科の一員としての診療にも従事しております。
私が主に診療しております肝臓がんの診療レベルは、この30年ほどでかなり良くなっています。その原因の一つは、肝臓がんの原因の大半がわかっており(ウイルス肝炎が約70%)、ウイルス肝炎の患者さん達を丁寧に経過観察することで、肝臓がんを早期発見できる体制が整ってきたことにあります。それ以外にも、肝炎ウイルス治療の画期的な進歩や肝臓がん診断方法や治療方法そのものの改善も大事な役割を果たしています。ここ数年でいくつか登場してきたC型肝炎に対する飲み薬の抗ウイルス剤は、それまで苦労していたC型肝炎ウイルス排除を100%近い確率で、しかも3か月程度服薬するだけで達成され、まさに画期的な新薬の登場となりました。また最近は、がん細胞の特徴を明らかにし、そこからがん細胞の弱点を見つけて治療するといった新しい薬剤(分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤など)が次々に開発されています。最近の医学はこのように絶え間なく進歩しているものの、がんに対する治療成績については、いまだ不確実な面が多い(同じ治療をしても著効する人もいれば、全く効かない人もいる)のが現状です。これに対し、がん組織の遺伝子を解析することで、がん細胞をやっつける治療効率を上げようとする診療(がんゲノム医療)が始まろうとしていますが、現段階では不確実性を完全に排除しきれるレベルではありません。
こういう状況において、患者さんたちが医療を受ける際、いかに納得・承諾して受けられるかが重要と考えています。それには、十分で正確な情報が必要であることは言うまでもありませんが、精神的な拠り所のようなものも、非常に重要と考えています。ジャパン・ウェルネスが発足して間もない頃、一度竹中の叔父に頼んで、見学をさせていただいたことがあります。その時、セカンドオピニオンとサポートグループに参加させていただきました。セカンドオピニオンは、かかっている主治医とは違った立場の医師から、情報を提供するというものですが、サポートグループは、患者さん同士の情報交換の場ということになります。このグループワークは、医療者の立場では提供できない情報+αを患者さんたちに提供できていると感じたことを覚えています。体験者だからこそ伝えられる情報や心情といったものではないかと考えています。その後、なにかの折に、叔父から「ウェルネスの経験者は、他の病院へ行った際に、肝が据わっているって言われるんだ」という言葉を聞いたことがあります。その言葉から、ジャパン・ウェルネスは、今の医療の手の届いていない部分をサポートしているんだと感じたものです。当時、自分の病院で「肝臓病教室」という患者さん向けの情報提供の会を定期的に開催していたのですが、その後この教室にグループワークを取り入れた次第です。
最近の医学・医療の進歩は、目を見張るものがありますが、ともすれば、特に我々医療者は“人間らしさ”を忘れがちになっているように感じています。がんサポートコミュニティーの活動は、医療の進歩を取り入れつつ、“人間らしい医療”を支えるしくみだと考えていますので、ますますの発展を期待しています。もちろん私もできる限り応援させていただければと考えています。
がんサポ通信・第34号(2018春)掲載

がん、再発・転移とどう向き合うか?~在宅医療でがんの苦痛を制する~
向山 雄人
東京がんサポーティブケアクリニック院長 元・がん研究会有明病院緩和治療科部長兼 緩和ケアセンター長
分子標的薬を中心とした新規抗がん剤の開発やゲノム医療の進歩により再発・転移がんのさらなる治療成績向上が期待されている一方で、がんに伴う苦痛への対処(緩和ケア・緩和医療)と抗がん剤治療など、がん治療の副作用への対処(サポーティブケア・支持医療)により、再発・転移したがんと共生する患者さんのQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質・人生の質)を支える医療体制構築が我が国のがん対策の最重点課題になっています。
私は32年間にわたり、腫瘍内科医、がん緩和ケア内科医として外来と病棟の最前線で再発・転移がんに対する診療に携わってきました。
2015年4月からは診療の場をがん専門病院から在宅へ移しましたが、2年半のがん在宅医療で患者さんやご家族が抱える苦痛・苦悩に関して一側面しか診ていなかったことに気付かされました。
そして、がん治療を受けている病院への通院・入院以外に患者さんが殆どの時を過ごすご自宅に定期訪問診療、緊急往診で伺うことで、初めて患者さんとご家族が真に望んで必要とされる緩和ケアと支持医療を提供できると思えるようになりました。
がんやがん治療による痛みや不安など、心身の苦痛・辛さを十分に把握して対処できなければ患者さんのQOLは急速に低下して行きます。
時間に追われ慌ただしい外来診療室では、ただでさえ緊張している患者さんは伝えたい症状を説明できない場合も多々有ります。それが自宅だとリラックスして細かいことまで話していただけます。
療養環境に関しても病院での診療では分からなかった点も見えてきます。患者さんの生活が見えなければ、最良のがん医療は提供できません。
抗がん剤治療を受けている場合でも抗がん剤治療が効かなくなった場合でも、きめ細やかな在宅医療を行い、患者さんとご家族にとって快適な日常生活が送れるように、医師・看護師・理学療法士・薬剤師・ソーシャルワーカーなどからなる「がん在宅医療多職種チーム」でサポートすることが求められています。
私が腫瘍を専門とした医師として以前から大切にしていることは、「病態をしっかり把握し発現する可能性がある症状・苦痛を予測すること、発現した症状に対する治療・ケアに関する複数の方法を持っていること、そして迅速に対応すること」です。
がん在宅医療を行っていて嬉しいことは、患者さんやご家族から、「苦痛や辛さに迅速に対処してくれた」と言っていただけた時です。
今回の第15回ペイシェント・アクティブ・フォーラムでは、どのような病態の時にどのような苦痛・辛さが出現し、それに対して今どのように対処すれば良いか、簡潔にお話したいと思います。
がんサポ通信・第33号(2017夏)掲載

大腸がん検診を受けましょう!
吉田 直久
京都府立医科大学附属病院 内視鏡・超音波診療部 講師
私は、大学病院で大腸がんに対する内視鏡診療および抗がん剤治療を専門として診療を行っています。これまで大腸がんの患者さんを2000名以上診療してきました。しかしながら、日本全体の大腸がん死亡は増加している現状に対して病院の中で診療しているだけではダメだと思い立ち、マラソンを通じてのがん検診をよびかける活動を3年前から始めました。「大腸がん検診を受けましょう!」というメッセージを書いたTシャツを着て全国のマラソンを走る些細な活動ですが、これを見た人がすこしでも検診を受診していただけたらと思っています。そして2016年の大阪マラソンではチャリティーランナーとしてがんサポートコミュニティーに寄付をさせてもらい大腸がん検診を沿道の方々に伝えながら2時間59分44秒で駆け抜けることができました。
【大腸がんの現状】大腸がんは、2015年のがん統計では約13万人が罹患し、日本人が最も罹患しやすいがんとなっています。死亡数も年間5万人を超え肺がんに次いで2位となり早急な対策が望まれています。大腸がんは40歳から年齢とともにその罹患数が増加することが知られており、典型的な症状は、便秘、腹痛、および血便ですが、早期の段階ではほぼ無症状です。早期のがんは90%以上が治癒しますが、進行したがんでは治癒が望めないことも少なくありません。ですので大腸がんの死亡数の低下には早期発見・早期治療が重要です。そのためには症状のない段階でのがん検診の受診が大切です。しかし日本は先進諸国の中でもっとも大腸がんによる死亡率が高い国になります。その原因の一つとして後述する検診受診率の低さが挙げられます。症状が発生してからの受診では治癒が見込めない進んだ状態でがんが見つかることも少なくはないのです。
【大腸がん検診】大腸がん検診では便中のわずかな血液を検出する便潜血検査が行われており、40歳以上で毎年の受診が推奨されています。約6%の方が陽性となり陽性の方は、精密検査として大腸内視鏡検査が必要となります。しかし、腸炎や痔でも陽性となることがあり、実際には約3%の方に大腸がんが見つかります。それでも検診陰性の方よりは何十倍もがんである可能性が高いので陽性となったら大腸内視鏡検査を必ず受けるようにしてください。便潜血検査は進行がんの方では90%程度陽性と判定されますが、早期がんでは60%程度にとどまります。ですから一回の検診では陰性となってしまうがん も存在しますので検診は必ず毎年受けることが重要です。しかし、日本において大腸がん検診受診率はわずか30%です。韓国では50%、米国では内視鏡検診を導入し60%を達成しておりさらなる検診の普及が望まれます。
【精密検査としての大腸内視鏡検査】大腸内視鏡検査は、お尻から直径1センチ強の長いスコープを入れて大腸を調べる20分くらいの検査です。強い痛みは10人に1人くらいに起きますが、細いカメラを使ったり、ベテラン内視鏡医がカメラの扱いを工夫することでずいぶん軽減できますし、希望があれば麻酔をしながら行うことも可能です。検査当日はたくさんの液体の洗腸剤を飲まなければいけませんが、最近は新しい製剤が登場し1リットルの洗腸剤で検査ができ味も以前に比べてずいぶんよくなりました。そして腫瘍の見え方を強調させる特殊なレーザー内視鏡なども併用し、より小さいがんの発見が可能となっています。さらに高度な内視鏡治療である内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を用いれば5センチにいたる早期がんであっても小型の電気メスを用いて切除することも可能です。これまで10年間で1000名以上のESDを行ってきましたが早期のがんであれば外科切除をせず体に負担の少ない内視鏡治療で多くの方が治癒されています。
最後になりましたが、種々のがんによる死亡数を減らすためにがんのことをより多くの方に知っていただく活動を続けられているがんサポートコミュニティーの活動に敬意を表します。
がんサポ通信・第32号(2017春)掲載
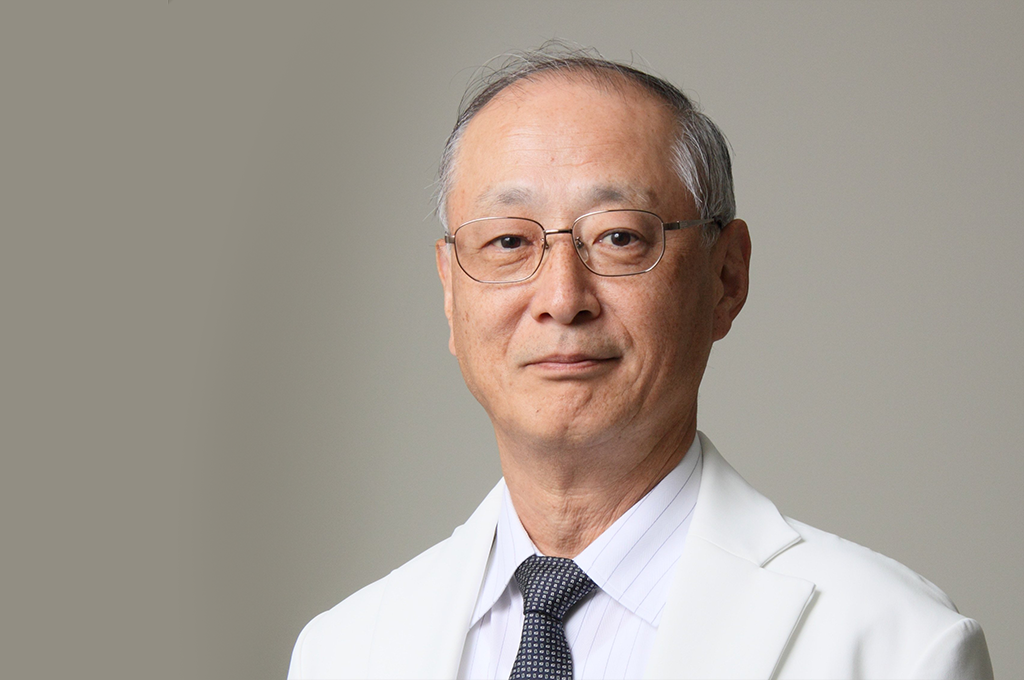
がん相談外来を始めてみて
江口 研二
帝京大学医学部難治疾患支援学講座 帝京新宿クリニックがん相談外来 特任教授
がんの診療ガイドラインと実際の治療
私が築地の国立がんセンター病院のレジデントとしてスタートしたのは昭和50年です。主に呼吸器領域の悪性腫瘍(原発性肺癌、多臓器がんからの転移性肺腫瘍、悪性中皮腫、胸腺癌、悪性リンパ腫など)の画像診断・内科的治療・緩和的医療を担当しました。その後も現在まで、進行肺がん、乳がん、消化器がんなどの悪性腫瘍診療を専門としています。特に最近のがん薬物療法は急速に進歩して、肺がん・乳がん・消化器がんなどの診療ガイドラインは、書籍版の改訂が間にあわず、各専門学会のサイトや公的な薬剤添付文書などで最新情報を補完しています。しかし、診療ガイドラインはあくまでも初級教科書であり、個々の患者さんの診療方針となると、教科書応用編になるわけです。そこで、医療機関では多職種専門家による定期的なキャンサーボード(患者さん毎の方針会議)が必要になるわけです。
“免疫療法”と“免疫チェックポイント阻害薬”
近年、多くの難治性進行がんで、抑えられている「がん免疫」を正常な機能に戻すような薬剤が、予想以上に治療効果を示し、世界に衝撃が走りました。免疫チェックポイント阻害薬といわれる薬剤で各国が短期間のうちに承認し使用され始めました。日本では、2016年7月現在、ニボルマブが進行非小細胞肺癌、悪性黒色腫にすでに承認されています。たとえると、進行がんでは人体内にいる警官(がん免疫)をだまして、警官が泥棒(がん細胞)を見つけることができないような状況になっています。ニボルマブは、警官と泥棒とのやりとりの場で、泥棒の化けの皮を剥がして、警官が適切に仕事するような効果があります。
いままでの「免疫療法」は、警官をいわば強力な軍隊にすること(攻撃力の増強)を狙ったものでしたが、このチェックポイント療法は逆に敵の化けの皮を剥がし、警官が捕まえやすくするのです。
現在でも免疫チェックポイント阻害薬以外の「免疫療法」は標準的な治療法ではありません。ネットで容易に検索できる“民間で行われている「免疫力アップなどと言う免疫療法」”は信頼に足りる大規模臨床試験などもなく、効果と安全性を適正に評価できません。
免疫チェックポイント阻害薬が承認され、「免疫」という言葉を使った民間療法が、がぜん勢いづいて、新聞・雑誌広告やネットに沢山出まわるようになりました。民間免疫療法の簡単な見分け方として、動物実験や少数の患者さんの印象記などしかない治療法か、治療法の経費の決め方、自分たちだけしか行っていない治療法か、抗癌薬などを併用しどれの効果かわかるのか、などをチェックしてください。
がんサポ通信・第31号(2016春)掲載

在宅で平穏な看取りを迎えるためには
吉澤 明孝
要町病院副院長 要町ホームケアクリニック院長
「看取り」という言葉は、日本語独特の表現である。本来(「看取りまたは看病り」とも書く)病人のそばにいて、いろいろと世話をすることつまり看病を指す言葉であるが、現在では臨終に付き添うことを指すことが多く、病人を看取る=看病とは取られず、気をつけなくてはいけない。しかし看取りは平穏な死、もしくは「お迎えが来た」といったソフトな別れのイメージがある。「看取り」の今の定義は「無益な延命治療をせずに、自然の過程で死にゆく高齢者を見守るケアをすること」と言える。つまり、慢性疾患を有する高齢者の終末期、がん末期の終末期において、緩和ケアを実践するということを意味する。また施設での看取りと在宅看取りでは、看取りに対する考え方、看取り方にも違いがある。
簡潔に言うと施設医療は、外来、入院ともに「治療(Cure)」であり、我々医療者が「ホスト」として患者、家族を「ゲスト」として迎えることになる。在宅医療は、「家族と楽しく過ごすことを支えるケア(Care)」であり、患者、家族が「ホスト」である城に我々医療者が「ゲスト」として訪問することになるのである。
それを踏まえて「看取り」を考えると、医療機関(入院)での看取りは、患者、家族にとって、ホストである医療者によってアウェイのゲストハウスで医療(治療)として旅立ちを確認されることになる。在宅での看取りは、家族がホームである城で家族として旅立ちを見送ることになる。それぞれに先に示した利点欠点がありどちらが良いとは一概には言えない。しかし、最近話題の「平穏死」「自然死」ということを考えるには、医療機関施設での看取りは不向きであることは確かである。医療機関では医療者は、対一人を看るわけにはいかず、変化を把握し対応する目的で少なくとも心電図モニターなどバイタルサインモニターの装着、点滴、酸素などの医療処置が施されることが多くなる。最近終の棲家としての老人施設、介護施設特に特別養護老人ホーム、グループホームなどで看取りがされるようになってきているが、やはり住所は移していても家族のいるホームとは異なり、医療施設とまではいかないが、最後まで胃瘻注入、血圧測定などが行われているところが多い。
先に述べたように在宅での看取りは、家族によって看取られることであり自然な経過での旅立ちを送ることができる場でもある。在宅では施設と異なり、本人の意思を尊重し(意思確認可能時)、本人意思確認不可であれば本人の尊厳を家族と相談し、家族の希望をかなえることも可能である。そのためには、死をタブー視するのではなく、日常の事として受け入れられる死生観の変革も必要になる。そのためにも、みんなで普通に話し合える機会(場)を提供するがんサポートコミュニティーの役割は大きいと考える。
がんサポ通信・第30号(2016春)掲載

この10年のがん対策を振り返る
垣添 忠生
がんサポートコミュニティー会長 (公益財団法人日本対がん協会会長)
この10年で、わが国のがん対策は大きく変った。
まず、がん対策基本法の成立。2006年6月のことで、2007年4月から施行された。
私は国立がんセンターの中央病院長を10年、総長を5年務めた。その15年間、わが国のがん対策は法律に根ざして展開されるべきだ、と繰り返し発言してきたが一顧だにされなかった。
ところが、島根県の大腸がん患者、佐藤均さんが、ご自分の化学療法体験から、島根県と東京では大きな違いがあることに気づいた。以来、佐藤さんは、「わが国のがん医療はおかしい」という発言と、それを正すための活動を展開した。2001年から2005年にかけてのことだった。2005年4月のNHKスペシャルで私は佐藤さんと共に出演したこともある。
そうした中で、がん患者、家族、国民の間から、わが国のがん医療に対する要望が亢まっていった。因く、地域間格差を解消してほしい、病院間格差を解消してほしい、そして、がんに関する情報格差を解消してほしい、というものである。この事が全国に広まっていくと、政治、行政が動き、2006年6月、ついに「がん対策基本法」が成立した。私にとっても大きな喜びだった。国会における審議過程で、民主党の山本孝史議員が、ご自分の進行がんについて触れ、「自分には時間がないのだ」という発言が審議の流れを変えたことを鮮明に覚えている。
2007年4月、がん対策基本法が施行されると、厚労省は直ちに、法律に規定された「がん対策推進協議会」を立上げ、私は座長を務めた。この協議会が画期的だったのは、協議会の委員にがん患者、家族、遺族の代表を加えて討論する、という点だった。
この協議会の議論に基づき、国のがん対策推進基本計画が閣議決定され、次いですべての県で県の基本計画が作成された。
国立がんセンター内に「がん対策情報センター」が設置され、情報の大切さに対応する中核機関となった。がん医療の均てん化を目指して、全国にがん拠点病院が約400指定された。法律制定と共にすべてが変っていった。
がん対策推進基本計画の前半5年では、五大がんの均てん化に焦点が当てられた。後半5年には、がん患者の就労の問題や、小児がん、希少がん、そしてがん教育にも注力された。
そう、法律が制定されたことで、わが国のがん医療は大きく変った。これをさらに充実させていくにも、患者、家族、国民の声は重要である。
そして、国の施策をサポートする形で、当がんサポートコミュニティーや日本対がん協会など民間の活動の重要性がいや増している。
がんはもちろん医療問題であるが、同時に社会問題であり、経済問題でもある。そして、医療従事者の活動の重要性と同様に、患者、家族に対する心理社会的支援活動も重要である。
その意味で創立15周年を迎えた当がんサポートコミュニティーの活動は今後ますます重要となる。なお一層強化していくために皆様方のご支援をさらにお願いしたい。
がんサポ通信・第29号(2015夏)掲載
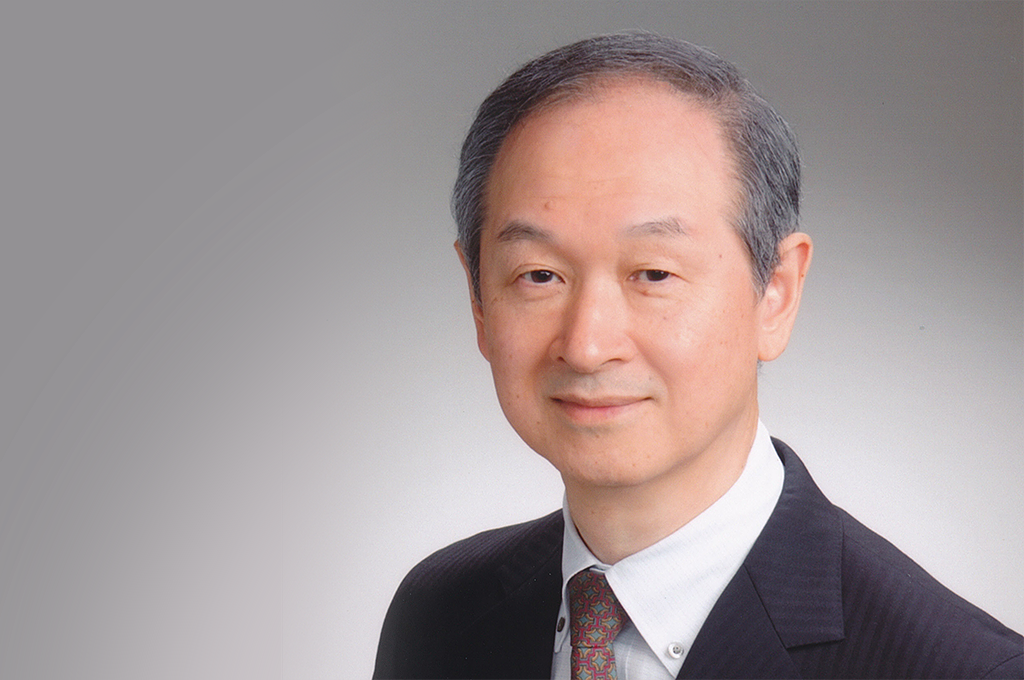
これからも共に歩いて行きましょう
渥美 隆之
がんサポートコミュニティー理事長(平山病院副院長)
がんサポートコミュニティーの活動は今年で15年を迎えます。がんと向き合わざるを得ない人たちが互いに話し、真に共感しあえる場を提供するということが、私たちの活動の中心であり基本です。しかし、これは言葉だけではなかなか分かりにくいようで、新興宗教のごとく捉えられていたり、「病気の話をすること自体、同病相憐れむようで嫌だ」などと私自身も親しい知人に言われたりしたものです。発足当時、支援者のみならず創設者である故竹中文良氏自身も3年続けられるだろうかと心配しておられたようでしたが、組織内外の多くの方々の力強い支援のお陰でこれまで活動を継続することができました。唯々感謝です。
さて、日本人の高齢化はさらに進み、団塊の世代が本格的にがん年齢に突入してがん患者数は増え続けています。しかも、まだまだこれから人生を有効に使おうと張り切っている年代の人たちに増えることになるわけです。当然、医療サービスの需要も著しく増加することになりますが、豊かな日本にとっても医療費はすでに重い負担となっており、何が必須の医療行為であるか、何にお金を掛けるべきかを真剣に考えざるを得ない時代となりました。
そもそも医療に関連している問題が、何でも病院でコストをかければ解決できるというわけではありません。疾患と関連する心理的、社会的な問題は多岐にわたり、そのすべての解決を病院に期待することには無理があります。何もしないでいるのは不安だ、ということで効果があまり期待できない治療を続けることや、終末期には入院するものという考え方も、ある意味で時代遅れなのかもしれません。アメリカではすでにこのような捉え方が受け入れられつつあり、米国本部Cancer Support Communityの活動は、そのような視点からも、とても有効であると期待されているようです。
今後も私たちの活動は「真に共感し合える仲間がいることが人の心を支える。真の共感の場を提供する。」という基本から決してぶれません。そして多くの方が参加し楽しむことができる合唱、アロマテラピー、ヨーガ、自律訓練法などのプログラムも、さらに充実させたいと考えています。加えて、私たちの活動を社会に広く知っていただく努力も大切だと感じています。私たちが同じところでのみ活動しているだけでは、私たちの信じている「よい物」を多くの人に知っていただき参加していただくことは難しいと考えるからです。
大阪マラソンからの寄付金を始め、関西圏の方々の支援をいただいたお蔭で2013年から大阪での定期的な活動を開始することができました。これを充実させ、さらに中部圏や別の地域でも、その地域の方々と協力しつつ活動の輪を広げて行きたいと考えております。
皆さん、これからも明日を充実した日々にするために共に歩いて行きましょう。
がんサポ通信・第28号(2015春)掲載
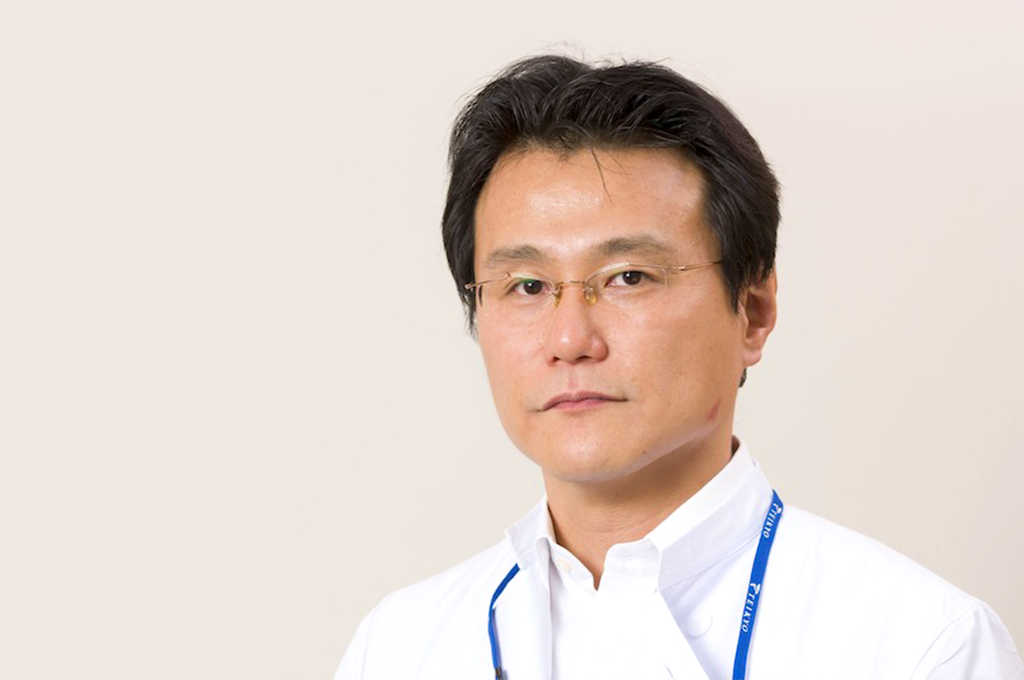
情報を見極め、決断・行動するために必要なこと
大野 智
島根大学医学部附属病院臨床研究センター長(寄稿当時、帝京大学医学部臨床研究医学講座 特任講師)
近年、インターネットの発達によって、誰にでも簡単に医療情報を入手できるようになってきました。その一方で、大量にあふれる情報に翻弄され、うまく活用できてない人も多いのではないでしょうか。 そのような状況を踏まえ、国立がん研究センターでは、『がん情報サービス』を立ち上げ、科学的根拠に基づいて情報を整理し、現時点で明らかとなっている正確な情報を分かりやすく紹介しています。また、厚生労働省は、多くの患者さんが興味関心を持っている健康食品・サプリメントなどの補完代替療法についても、『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』の一環として、『「統合医療」情報発信サイト』を立ち上げました(この事業には、私自身も関わらせて頂きました)。 いずれのサイトの情報も、重要視しているのは科学的根拠です。別の言い方をすれば、臨床試験などの研究結果から導かれた「裏付け」と理解していただければと思います。 ただ、これらのサイトの情報をみてみると、「〜と考えられます」「〜の可能性があります」などの曖昧な表現が多く、断定的な文章を見ることは余りありません。その一方で、「100%の治癒率」「絶対安全」などといった宣伝文句を見たり聞いたりしたことがある人もいるかもしれません。果たして、どちらの情報が、正確な説明の仕方なのでしょうか? 実は、医療情報というのは、なかなか白黒がはっきりとつけられるものではなく、ほとんどは灰色であるのが現実であることを是非知っておいて下さい。治療法を選択する際に、臨床試験で明らかとなった数字は、判断材料として重要な意味を持っています。しかし、医学・医療は万能ではありません。治療効果が100%で、副作用が0%という治療法は残念ながらありません。また、臨床試験の結果も、参加した患者さんの「集団」を対象とした値であって、個人にとって、効くか効かないかは、やってみなければわからないという悩ましい現実があります。 「できるだけ健康に良いことをしたい」「効果のある治療を受けたい」という思いは、多くの人々に共通の願いだと思います。そんなとき、誇大な宣伝文句に惑わされないための、情報を見極める目を身につけていただきたいと思います。 そして、情報を見極め、取捨選択し、それをもとに決断して行動することになります。決断は、「するか、しないか」ですから、白黒をつけなければなりません。ここで「灰色(の情報)から白黒(の決断・行動)へとジャンプする」ということになります。 医療では、すべての患者さんが同じ情報をもっていても、価値観によって選び方は異なってくることがあります。「なぜ生きたいのか?」「どう生きたいのか?」など個人個人の人生観や死生観によって、治療方針の決定(決断)は千差万別になります。残念ながら、医療情報に、「するか、しないか」といった答えはありません。あくまで患者さん自身が判断するための材料を提供してくれるだけです。 人生の判断をするための価値観。すぐに答えが見つかるわけではありません。また、正解があるわけでもありません。しかし、患者さん一人ひとりが、ご自身の体の責任者として、人生の意義や使命、希望について、一度、考えてみてはいかがでしょうか。
がんサポ通信・第27号(2014夏)掲載

地域のコミュニティーとしてのサポートグループ
小川 朝生
国立がん研究センター東病院 臨床開発センター精神腫瘍学開発分野長
2013年にわが国は65才以上の人口が25%を越え、未曾有の超高齢化社会を迎えています。近頃はニュースのあちこちで高齢化が連呼されるため、20%以上という数字にもいつの間にやら慣れてきてしまった感があります。しかし、過去を振り返ってみると、今の近代医療が育ち始めた1900年代の高齢化率は1%、近代ホスピスが芽生え、生活の質を医療が問い始めた1950年代でもせいぜい10%であったことと並べてみますと、医療をとりまく前提条件が、大きく様変わりしてしまったことを改めて感じざるを得ません。 高齢化が進むことでの問題として、第一に支える社会体制の負担が大きくなっていく点がしばしば指摘されます。たしかに、負担の増大も課題ではありますが、医療の今後を考える上で意識しなければならない点は、高齢化の問題の現れ方が地方と都市部で違う点です。まず、地方では、高齢者人口の増加は多くとも30%程度に留まるのに対して、東京や大阪など大都市近郊では、70%から100%も急増する点です。特に、この傾向は東京近郊で著しく、医療の支援を受けながら地域で暮らす体制をどのように作るかが課題となります。このような支援を目的として提唱されているのが、地域包括ケアであり、その実現に向けて、地域ごとにどのように取り組むかが議論されつつあります。 当然、医療をどのように提供するかが大きな課題となりますが、医療とあわせて問題になるのが、支援体制をいかに地域につなげていくか、という点です。今、好事例として取り上げられる地域は、主に地方であり、その地ではもともとネットワークが密にあり、生活をお互いに支える文化があります。しかし、今後問題となる都市部においては、個人のプライバシーをお互い重視し、他人の目を気にしなくてもよい反面、たとえ近所であってもお互いの生活を知らず、生活に助けが必要となった場合に、助けを出すことが難しくなった面があります。また、助けを求めたいと思ったとしても、個別のニーズを強く持っていることもあります。単に近所の「世話焼きおばさん」がいればいいというわけにはいかない難しさがあります。 このような地域では、ニーズや情報を基盤とした新たなつながりが期待されています。これは情報やニーズに沿った支援、サポートグループの志向と一致します。がんサポートコミュニティーが目指す支援は、参加者個人個人のニーズに応じたコミュニティーの場を作るのみならず、必要な医療にもつながる場でもあり、新しい地域医療のネットワークとしての役割も担っています。 共有できる「場」として、「何かちょっとしたことでも」発信できる・受ける担い手として、サポートグループからの発信と展開に期待をしています。
がんサポ通信・第26号(2014春)掲載

自分らしさの回復のために
遠藤 公久
がんサポートコミュニティー副理事長 (日本赤十字看護大学教授)
私は創設以来、主に消化器系(胃・食道)のグループならびにご家族のグループのファシリテーターをさせていただいてまいりました。当然のことながら、お一人お一人の人生が異なり、価値観が異なるように、がんの症状もその捉え方もそれぞれかと思います。私たちファシリテーターは、そのような多様性のあるグループのなかで、それぞれの参加者が素直に語り合い、お互いに<癒しー癒される>関係になれるにはどのようにすればよいかということを考えお話を聞かせていただいております。
がんになると、身体的、心理的、社会的、そして実存的側面における全人的な喪失を体験するといわれます。そのような喪失体験は、自分や将来への不確実さを強めます。私は、このような喪失体験のなかでも、とりわけ、「(生きる)意味の喪失」(「なぜ自分か」「なぜ今か」「がん人生にどんな意味があるのか」)「関係性の喪失(孤独の問題)」(「誰が今の私を理解できるのか」、「患者でなければ理解してもらえない」)「アイデンティティの喪失(自由の問題)」(「今の私に何ができるのか」「がんに罹患した私とは一体何者か」)などの問いかけや思いは、生きる意欲と深く関わる重要な問題だと思っています。
人は一般に困難に直面しますと、そのことを「認めたくない」「何も考えないようにする」「負けない」「ただ前向きにがんばろう」と、その問題から回避したり、否認したり、心の奥に押し込もうとしたりすることが多いかと思います。しかし、いくらそうしても、例えば、就寝前や夜中目が覚めてふと将来への不安が意識に昇って眠れなくなったり、新聞に掲載された記事や広告の「がん」という言葉に過敏になり、急に不安が強まったりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。心は、その問題があまりに重大だと意識的にコントロールすることが難しくなります。そのようなしまいきれない心の問題を回避や否認や抑圧するには多くのエネルギーを必要とするようです。
それでは、どのようにして少しでも心の安寧を取り戻し、その人らしさを回復することができるでしょうか。私はここでは三つのことをあげたいと思います。
一つは、正しい情報を得ることです。例えば、最新治療法、検査データの正しい知識、術後の回復過程、抗がん剤の副作用の理解、転移後の自分の辿ると予測される病態変化などがあげられます。そうすることで、現在の自分あるいは今後予想される自分の状態について理解が深まると少し安心かもしれません。
二つめは現実の問題に対して何とかなるとか、何とかやっていけるという感覚を取り戻すことです。術後直後しばらくの間は頭からがんのことが離れない事が多いので、本人も家族もがんについて考えない時間が必要です。瞑想や自律訓練法などのリラクセーション法、ウォーキングや軽い体操、コンサートに行くなど、自分でストレスを緩和させる方法を見出すことで少し自分に自信がもてるかと思います。
そして、最後におそらく最も大切なこととして、思いや不安を表現することだろうと思います。文章にしてみたり、言葉にして誰かに聞いてもらったりして直接表現することもあるでしょうし、絵や音楽を通して間接的に自分を表現することも含まれるでしょう。たくさんの人がウェブに闘病日誌に残したり、闘病記を上梓したりしています。絵や写真に自分の思いを重ねることも一例かと思います。
とりわけ、同病者同士における語り合いは、単なるモノローグではなく、真の意味での交流であるとき、お互いが<癒し―癒される>関係へと発展していけると私は信じております。そして、そのような語りの中から、生きる意味や病の意味を見出せるのではないでしょうか。
がんサポートコミュニティーでは、正しい情報提供のために、ペイシェント・アクティブ・フォーラムやがんを学ぶセミナー、そして複数の医師によるがん相談を設けております。また、ストレス緩和、自信回復のために、様々な補完療法(とくにリラクゼーション法)のプログラムがあります。そして、間接的な自己表現として、コーラス(合唱団いきのちから)などもあります。サポートグループでは、お互いの語りのなかに<癒し>の場が設けられますように、ファシリテーターも微力ながらお手伝いさせていただいております。
がんサポートコミュニティーでは、皆さまの自分らしさの回復のために、少しでもお役に立てますように、このように多様なプログラムを用意しております。忌憚ないご意見を頂戴できれば幸甚です。
がんサポ通信・第25号(2013夏)掲載
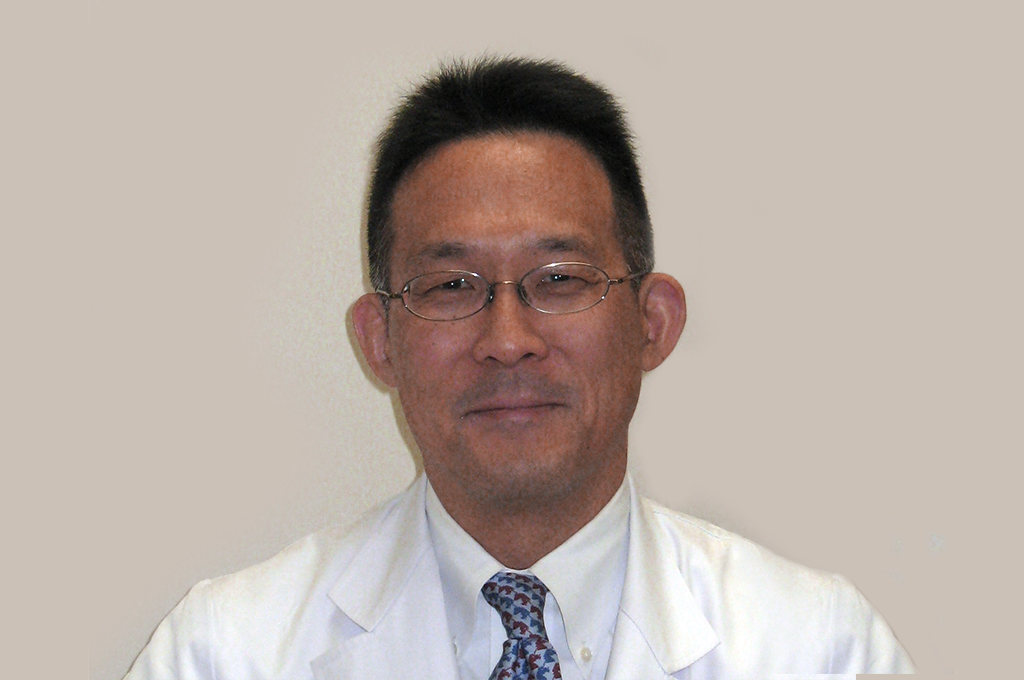
がんと共に歩める社会を目指して
藤原 康弘
がんサポートコミュニティー顧問 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 (寄稿当時、国立がん研究センター企画戦略局長 兼同中央病院 乳腺・腫瘍内科 科長)
私はがん専門病院で乳がんを中心にがん患者さんの診療に従事する内科医です。医師となって29年、途中、研究所での研究者としての生活、大学医学部附属病院での教官としての生活、米国留学、新薬の承認審査部門での審査官、内閣官房でのイノベーション戦略立案と様々な経験をしつつも、キャリアの半分は呼吸器内科医として、そして最近の10年は腫瘍内科医として、がん患者さんの診療は一貫して続けております。
研究者としては抗がん剤が効かなくなる機序解明と克服方法の開発の研究をしておりましたし、大学では肺癌診療の専門医の育成に関わり、留学中は抗がん剤の第Ⅰ相試験(はじめて人間にクスリを投与する段階)の研鑽を致しました。米国留学から帰国直後、エイズ薬害事件を契機に発足した医薬品医療機器審査センター(以下、審査センター;当時は日本版FDAとも呼ばれていました)に、薬事行政なんて右も左もわからない中、医師の審査担当官の初代となって赴任した時期が人生最大の転機でした。上京しての転勤とほぼ同時期に脳梗塞後遺症の義母の面倒をみつつ設計事務所をやっていた30代の義姉を乳がんで失い、新しい仕事に加え、介護も手伝うという二足のわらじは、きついものでした。その経験が、「ドラッグ・ラグ解消と創薬立国を実現する」という自分の仕事の目標と「がん患者さんに寄り沿いながら、家族の皆も支える」という診療における基本姿勢を育てることに大きく貢献してくれたと思っています。
審査センター発足直後、いや今でもですが、新薬審査は役人が業界や大学医学部の大教授たちと癒着しつつ進めているという批判を耳にしますが、実際の新薬審査の現場を経験してみて、それは完全な誤解であると断言できます。審査官時代を含めて何度も海外の規制当局を訪問しましたが、英語での会話力を除いては、日本の審査官の能力は米国やEUと比べても格段に優れたものです。ここ数年で、ようやくEUの中央審査部門(EMAと呼ばれています)並の職員の数(700名弱)となりましたが、EUでは各国に、中央部門とは別に審査や薬の安全対策を担当する官庁があるので、創薬・育薬(iPS細胞などを用いる再生医療なども含め)を日本が世界をリードし、国民が世界で最新かつ最良の医療を享受するためにはもう一歩のマンパワーの強化が必要であることを皆さんには知って頂き、応援してもらいたいです。また、ドラッグ・ラグの苦しみを役人はわかっていないとの批判も聞きますが、審査センター時代の同僚や先輩、後輩、皆、自分ががんを罹患しこの世を去ったり、抗がん剤治療でがんと戦いながら新薬を渇望していたり、がん患者の家族として介護をしています。役所を敵とするのではなく、敵とか味方という概念を捨て、皆でスクラムを組んでがんという難敵に戦うという気持ちが大事だといつも思っています。
一方、がん診療をみてみると、留学時代に見た「経済的余裕の程度により受けることのできる医療が変わる」米国型医療の負の部分を皆でもっと認識しないといけないと感じます。米国の新薬審査部門のFDAという官庁が薬を承認しても、高額な価格とべらぼうに高い医療費あるいはそれを受けるのに必要な毎月の高い保険料のために、存在するクスリを自分に使えない(「インシュランス・ラグと米国の新聞記者さんは名付けています)状況を私は日本で再現したくありません。国民皆保険の維持に加え、患者、患者家族のみならず広く国民皆や製薬産業以外の企業も寄附をして国民基金を創設してインシュランス・ラグに備えることも解決策のひとつになると思っています。
さらに働き盛りの患者さんを日夜診療する中、仕事・就業とがんとの付き合いの両立が如何に難しいものかを日々実感させられます。さらに高齢化社会となり独居の方が増えている都会での在宅医療の困難さも感じます。「がんと共に歩める社会」を目指すには、診断・予防・治療の進歩に加え、さまざまな社会制度改革も必要です。医師vs患者、役人vs患者団体といった対立する構図を想定するのではなく、いつかは自分も罹患するであろうがんという疾患のみを見据えて、皆でこの難敵に立ち向かっていきましょう。
がんサポ通信・第24号(2013春)掲載

認定特定非営利活動法人
がんサポートコミュニティー
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3丁目10-4 虎ノ門ガーデン214号室
TEL. 03-6809-1825 FAX. 03-6809-1826